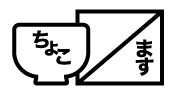2023/07/27(木)、私が仕事で南浦和に行っていた日、
東京ドーム近辺で、友達と遊んでいる子供たちの写真が多数、楽し気で結構。
Author Archives: なおみ
4441、庵悟 3.64、個人.3.3
2023/07/27(木)、営業先ランチ、庵悟 3.64、個人.3.3、
南浦和?駅からも結構遠いし、何処に行った時なのか?まったく思い出せん。
4440、札幌味噌らーめん 葵葉 荏原中延店 (アオバ) 3.49、個人3.7
2023/07/26(水)、営業先ランチ、札幌味噌らーめん 葵葉 荏原中延店 (アオバ) 3.49、個人3.7、
美味しいのだから、もっと塩分抑えればいいのにの味だが、まあ、美味しいからよいとするか。
4439、閉店 麺や 麦ゑ紋 (ムギエモン) 3.67、個人3.7
2023/07/24(月)、営業先ランチ、閉店 麺や 麦ゑ紋 (ムギエモン) 3.67、個人3.7、
大カード近くは仕事で結構行くので、ラーメン店が乱立していて、入替も激しく、助かる。
美味しかったと思うのだけど、それでも続かない。
4438、親になる no.297、長女二回目のわくわく発表会
2023/02/07(土)、年中に長女、幼稚園行事、二回目のわくわく発表会でした。
うめ組の演目は「3じのおちゃにきてください」
かえる、うま、ねこ、らいおん、チームが各々のゲームで遊ぶ。
ジャンプかえるケロゲーム、へびにょろにょろゲーム、縄跳び、火の輪潜りをし、
かえるの家に集まるという筋。
もうなんですか、特になんという思いもないですね、
アイムソーリーとは思いますが。
4437、亀戸 焼鳥のんき 3.35、個人3.3
地元に戻りながら、亀戸 焼鳥のんき 3.35、個人3.3、
今知ったが、のんき系列なのね、高くなく質高く、席狭め、みたらし団子があり、
子供は嬉しい系列、個人的にもよし。
4436、ヴィオレッタ (VIOLETTA) 3.26、個人3.1
東小松川公園は、駅からは結構遠いので、飲食店も期待はできず、
ヴィオレッタ (VIOLETTA) 3.26、個人3.1、
これでもかという個人経営で、ひっとしたら大当たりもある作りながら、
そうでもないものの、まあ。
4435、東小松川公園
2023/07/23(日)、自転車40分、東小松川公園、
>全長およそ3,900メートルほども続く「小松川境川親水公園」に隣接している公園です。春にはお花見、夏には水遊びが楽しめます。水遊び場には、たくさんの水が溢れ出す岩山のほか、木製の大きな船があるじゃぶじゃぶ池。海賊気分を味わいながら水遊びが楽しめます。その他にも園内には魅力がいっぱい! 背中に乗ったり、すべり台としても遊べる恐竜や、おままごとに利用できるお家の造形遊具。すべり台がついた幼児用の複合遊具や太鼓橋などもありますよ。
引用終わり、
じゃぶじゃぶ池は、岩山と船が代替が利かないし、虫取りレベルも高いので、頭一つ上なんだが、
とにかく、うちからは遠いのよね。
4434、「第45回足立の花火」
ということで、この日のラスト、「第45回足立の花火」、
>東京で開催される大規模花火大会の先陣を切り、7月下旬に開催するのが「足立の花火」。実に4年ぶりとなる「第45回足立の花火」では、荒川河川敷でわずか1時間の間に約15,000発の花火を打ち上げます。迫力が凝縮した、高密度な花火をぜひお楽しみください。
引用終わり、
そうか、花火大会というものが、結構それなりぶりなのだな。
花火大会に、自転車で行けるのなら、帰り混まなくていいなとは思うけど、
北千住は遠い。
ああ、河川敷なら、どの範囲で見えてるのか知らんけど、
混んでなくてよい。充分なんでないかな。
4433、炭火焼肉 はな火 3.15、個人3.1
この日はもりだくさんだ、この後北千住まで自転車で花火を観に、
手前三ノ輪でディナー、炭火焼肉 はな火 3.15、個人3.1、
雰囲気は悪くない感じがしたのだけど、評価通りの微妙さ。