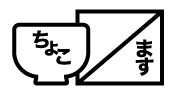2022/05/27(金)、近所家族ディナー、333 ベトナム料理 (バーバーバー) 3.42、個人3.3、
ほぼ覚えていないが、まあまあと。
Author Archives: なおみ
3862、麺屋海神 新宿店 (めんやかいじん) 3.76、個人3.4
2022/05/25(水)、勤務先近所ランチ、麺屋海神 新宿店 (めんやかいじん) 3.76、個人3.4、
ここも評価の理由がわからない店で、まあ、普通よりは頑張ってるかな、という感じ。
麺が柔らかかった気もする。
3861、らーめん こてつ 3.62、個人3.5
2022/05/24(火)、営業先ランチ、らーめん こてつ 3.62、個人3.5、
新所沢などに何しに行ったのかも思い出せず、店もどうだったのかなぁ。
3860、味噌らーめん 十味や 新宿 (とおみや) 3.49、個人3.6
2022/05/23(月)、営業先ランチ、味噌らーめん 十味や 新宿 (とおみや) 3.49、個人3.6、
新宿の東口もラーメン激戦区、美味しかったようだ。
3859、船に乗る
2022/05/22(日)、写真が港区海岸なので、竹芝だか日の出桟橋だかから船に乗り、どこで降りたかわからん。
相変わらず相方が何かに応募し当選したのだろうから、お金は払っていないと思われ。
3858、アジアンビストロ Dai 日本橋店 3.42、個人3.4
2022/05/21(土)、中野へしまじろうコンサートを観に行き、
友人と食事をして、地元に戻り、アジアンビストロ Dai 日本橋店 3.42、個人3.4、
高島屋なので使い勝手はよく、そんなに高くはなかったか。
3857、ラーメン見田家 3.54、個人3.2
2022/05/20(金)、営業先ランチ、ラーメン見田家 3.54、個人3.2、
家系で評価が低いのは単純にしょっぱ過ぎ。
3856、カネキッチン ヌードル (KaneKitchen Noodles) 3.79、個人3.6
2022/05/19(木)、営業先ランチ、カネキッチン ヌードル (KaneKitchen Noodles) 3.79、個人3.6、
ここも評価で期待したものの、なんかそこまでかという店。
なかなか評価通り美味しいと思える店に出会えるということはない。
3855、閉店 豚そば 月や 東京 3.68、個人3.6
2022/05/17(火)、営業先ランチ、豚そば 月や 東京 3.68、個人3.6、
広尾というところは、イメージはいいんだろうけど、街自体は狭いので、
そこまでいけてる飲食店が多いわけではなさそうな中、
新しいビルにおしゃれな店がいくつかできたけど、
そうそう、うまくいくもんでもないと。
3854、切麦や 甚六 3.65、個人3.4
2022/05/16(月)、勤務先近所ランチ、切麦や 甚六 3.65、個人3.4、
当時も今もかなりの人気で、悪天候とかでない限りすんなりは入れない店。
とはいえ、そこまで美味しいかというとと。