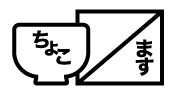1618年、本多忠政、鷺山に西野丸を築く
1639年、松平忠明が大和国郡山から入封
1648年、松平直基が出羽国山形から入封
1649年、榊原忠次が陸奥国白河から入封
1667年、松平直矩が越後国村上から入封
1682年、本多忠国が陸奥国福島から入封
1704年、榊原政邦が越後国村上から入封
1749年、酒井忠恭が上野国前橋から入封
城下大洪水の被害
1808年、家老・河合道臣が財政改革に着手
(1787年、21歳で家督を継ぎ、姫路藩家老に。
1808年、ときの藩主酒井忠道から負債73万両に膨らんだ
姫路藩財政の立て直しを命じられる。
姫路木綿の江戸専売権取得や様々な運営事業を行い、
1834年には負債を完済。)
松平、酒井、榊原と親藩、譜代がずっとなので、やっぱり重要な拠点だったのだろう。
そんで、陸奥とか越後とか同じ流れで来る人が多いのは、今も昔も出世コースみたいなのがあったということ?