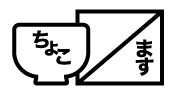「瓦、姫路城の瓦は、平瓦と丸瓦を交互に組み合わせた本瓦葺で、
継ぎ目には屋根目地漆喰が一面に施され、
甍(いらか)の美を表現しています。
歴代城主の修理の歴史を物語るがごとく、
鬼瓦、軒丸瓦などに多様な城主の家紋などが残っています。
現存するものだけを数えても8種類あります。
門、姫路城には菱の門、「いろは・・・る」の門、「水の一・・・六」の門、
備前門が現存しており、その様式は実にさまざまです。
防備面から頑丈さを重視した柵門や木戸、掘重門、
冠木(かぶらぎ)門、高麗門、櫓門、長屋門、埋(うずみ)門など、
安土桃山時代の様式を残す門など21門が残っています。
狭間、狭間とは天守や櫓、土塀の壁面に開けられた矢や鉄砲を放つための穴のことで、
城を防備するための重要な仕掛けでした。
一般的には丸型や三角型、正方形(鉄砲用)、縦長方形(弓・矢用)の4種類。
現存する狭間の数は997ヵ所。
開けられた位置によって立狭間、居狭間、寝狭間とも呼ばれるが、
姫路城は片膝を突いて鉄砲を撃つ時に使われる居狭間が数多く見られます。」
ということで、入れるのは天守閣だけではなく、ここは百間廊下と呼ばれる建物でした。