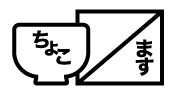いきなりそういう看板が外にあるくらいそれ押しなんだが、養源院、の血天井。
>秀吉の側室淀殿が父浅井長政の供養のため創建。その後、徳川秀忠の正室崇源院(江)により再興された徳川家の菩提所で,歴代将軍の位牌をまつる。
方丈の襖と杉戸絵は俵屋宗達作、また廊下の天井は、伏見城落城の際、自刃した武将たちの血のりのしみた「血天井」として知られる。
>慶弔5(1600)年に徳川家の陣であった伏見城に、約4万もの兵士を引き連れてきた豊臣方の軍勢に破れ、約2,000人いた徳川方の軍は380人余までに減少。
伏見城を守っていた武将・鳥居元忠を筆頭に残った兵士は「中の御殿」に集まって自刃し、伏見城は落城しました。
その後、養源院再興の際に元忠らの菩提を弔うため、床板は天井に上げられました。
本堂の天井では380余人兵士の血痕や、元忠が自害した場所といわれる跡がくっきりと残されています。
引用終わり、
くっきりというのは盛っているとしてもまあ血痕であろう、と思われるものはしっかりとある。
それから、
> 【江戸の有名絵師・俵屋宗達の絵画】
安土桃山・江戸期には狩野派の画家が寺院やお城の襖絵を描くことが多く、養源院にも狩野山楽が描いた襖絵が残されていますが、
当時無名だった俵屋宗達が認められるきっかけとなった奇抜で斬新な絵が多く残されています。
特に『白象図』や『唐獅子図』は、現代の3D技術にも匹敵するといわれるほど、杉戸の中から今にも白象と唐獅子が飛び出してくるかのような技法で描かれています。
引用終わり、
たしかに面白い絵です。
非常にこじんまりとしている観るスペースは2、3なんだけど、
説明がしっかりしているので見どころがあったね、という満足感があるとこ。
智積院に比べると知名度低めだが、近いし、三十三間堂か京都国立博物館に行くなら是非寄るべし。