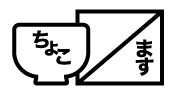お酒を飲めない人を下戸と言いますね。
以下、Wikiから。
>古くから日本では、酒を全く飲めないか、または飲める量が他と比較しても少ない人を「下戸」と呼び、
その対義語には「上戸」が宛てられる。
「戸」とは律令制における課税単位のことであり、元来、最上位の大戸から、上戸、中戸、下戸と定めた上で
婚礼時の酒量を決めたことから、転じて酒を良く飲む人を上戸(または大戸)、
余り飲めない人を下戸と呼んだのが由来とされる。
なるほど。
上戸はじょうごと読むらしい。いやはや、知らんもんです。
何が凄いって、再度Wiki。
>日本の律令制は、概して7世紀後期(飛鳥時代後期)から10世紀頃まで実施された。
わざわざ、お酒が飲めない人のことを言うのに、
どんだけ古い頃からの言葉が残っているんだということ。
そりゃあ、当時はお酒が飲めるか飲めないかは
裕福かどうかの物差しであったのかもしれないけれど、
その後、その物差しって、米というか石高制になったわけじゃない。
古い言葉が残っているのは大いに結構なんだが、
ここまでたどり着く前に、
残しつつも、もっといい感じの言葉を作ってきとけよ、日本人、
と思う次第。
ところで、綾戸智恵の「上戸彩ちゃうでー」はてっぱん。