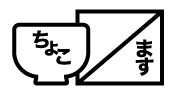それまで存在を知らないし、世の中にはこういうとこもあるんだなぁと思った、耕三寺(こうさんじ)、
>耕三寺(こうさんじ)は、広島県尾道市(生口島)に所在する浄土真宗本願寺派の仏教寺院。
>山号は潮声山(潮聲山)。
>1936年(昭和11年)から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」「母の寺」とも呼ばれる。
>このうち、山門・本堂をはじめ15の建造物が国の登録有形文化財として登録されている。
>また、仏像、書画、茶道具などの美術品・文化財を多数所蔵し、寺全体が1953年3月14日より博物館法による登録博物館となっている。
>無檀家寺院でもある。
>沿革
>耕三寺の開山は、大正・昭和期に大阪で活躍した実業家の金本耕三のちの耕三寺耕三。
>1927年(昭和2年)故郷瀬戸田に住む母のために邸宅「潮聲閣」を建て始めた(耕三寺内に現存)。
>母が1934年(昭和9年)に没すると、翌1935年(昭和10年)、金本は母の菩提を弔うため出家して僧侶となり名を福松から「耕三」に改め、同年から母への感謝の意を込めて、潮聲閣周辺にて耕三寺の建立を開始した。
>金本はかねてより、瀬戸田の地に誇りうる文化財のないことを残念に思っており、境内を日本各地の著名な歴史的建造物を模した堂宇で埋める構想を立てた。
>以来、30余年をかけて、日光東照宮陽明門を模した孝養門、平等院鳳凰堂を模した本堂などをはじめとした伽藍が完成した。
>なお金本は1956年(昭和31年)以降、自らを「耕三寺耕三」と名乗るようになった。
>陽明門を模した孝養門から「西の日光」と呼ばれるようになり、瀬戸内海の観光地の一つとなった。
>平成期に入ってからは、建築物の特殊性が評価され、15棟が登録有形文化財として登録された。
引用終わり、
ということで、
何も知らんで観ているうちは、あまりにも豪華なのが、
なんか悪趣味というかこれはテーマパークなのかくらいに思ってみてまして、
寺なんてものはある程度古くないと
ありがたみも何もねぇ
ということで、
正直知らなかった実業家が、
母親を弔うためにどんだけ金かけてんだと、
少なくともうちの親がそういうことをし始めたら
全力で止めるようなことをとんでもない規模しているなと、
ただ、落ち着いて考えると、
例えば、京都三十三間堂の近くにある養源院というお寺は、
>文禄3年(1594年)に豊臣秀吉の側室・淀殿が父・浅井長政、祖父浅井久政らの二十一回忌の供養のために秀吉に願って創建した。
>浅井氏の菩提寺。
引用終わり、
つまり、親のためやら誰かのためにとんでもないお金をかけて寺を作っちゃうことはままあって、
この寺もそれなりの月日が流れたら、
他の寺と同じようになるのかなぁ、
などと思いつつも、
しっかし広いなぁ、どんだけ金かけてんだよと、しつこく思うのでした。
ところで1,400円するんだよね、高いから。