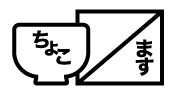ついでに、風立ちぬ、という意味を考察。
以下、引用。
・風立つ: 風が出てきた。
「立つ」とは、その時に、風が一回だけ、さあっと通り過ぎたというものではなく、今まで静かだった辺り全体に、風が吹き始めたという感じです。
・(風立ち)ぬ: 完了・強意の助動詞終止形。
動詞が示す動き(ここは風立つ)が完了したことを示します。
ということで、「風立ちぬ」は「風が立った」とか「風が出てきた」などと考えればいいと思います。
・いざ: さあ、いよいよだ
「さあ、でかけよう」にくらべて「いざ、出発」と「いざ」を使うと強い意思を感じるようになります。
・(生き)め: この場合は意思の助動詞「む」の已然形
意思:生きていこうか
「可能」ととれば「生きることができるだろうか」になります。しかし、ここは意思でしょう。
・(生きめ)やも: 反語の助詞
「~か、いや~ではない」
ということで、「いざ生きめやも」は「さあ、生きていこうか、いや死のう」という意味になります。
しかし、出典である堀辰雄の「菜穂子」の内容からいけば、「生きていこうか、生きていくまいか、いや生きていくぞ」という意味の方が合っています。大学では、「文法と解釈」を考える題材としてよく取り上げられるようです。
ちなみに、もともとのヴァレリーの詩は、
「風が立った、私たちは生きようとしなければならない」といような意味です。この意味であれば、読者が望む形で「菜穂子」の内容ともピタリ合致します。しかし、堀辰雄はそう書かなかったわけです。「なぜでしょう?」というのがポイントになるのでしょうね。
以上、引用終わり。
いやね、日本語って難しいね。