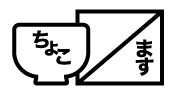坂出からまた高速のって、観音寺まで。
38年生きてきましたが、
観音寺は、かんおんじと、観音寺市は、かんおんじしと読むことを、
土曜日にはじめて知りました。
まあ、発音上は、知らない、ということがばれない気もする。
69番目の観音寺を目指しまして、
68番目の神恵院は同じ場所にあります。
じんねいん、と読むらしい。
結構、こじんまりとしてます。
特に拝観料とかかからないのね。
そして、車でお遍路をしているらしく、
あの衣裳の人が多少いるんだが、
車で回るんなら、その服きてもさ、と思った次第。
ほんのちょっとしかいなかったのだけど、蚊に刺されました。
まだ時間がちょいとあったので、次はこちら。
これもなんとなく知ってますね。
琴弾公園と書いて、ことひきこうえんにある、
銭型砂絵、寛永通宝と書いてありますね。
>縦122メートル、横90メートル、周囲345メートルの楕円形をしており、琴弾公園山頂の展望台からみると真円に見える。夜になるとライトアップされる。
謂れは「1633年(寛永10年)に、丸亀藩藩主の生駒高俊侯が領内を巡視することになった折、土地の人々が歓迎の気持ちを現わすため、急遽白砂に鍬を入れ一夜にして作りあげて藩主に捧げた」と伝え説明されているが[1][2]、寛永通宝が鋳造されたのは寛永13年(1636年)からであり、また高俊が巡視した事実もなく、その点でこの伝承には矛盾がある[3]。また、「1855年(嘉永7年/安政元年)に丸亀藩第7代藩主京極朗徹に見せるために造営された」説や、「もとは豊臣氏の瓢箪紋だったが、寛永10年に幕府の巡検使が来ることを知って一夜で作り変えられた」という説もあるが、決定打はない[3]。
とのこと。
現場には、最初の説しか書かれていません。
まあ、どうでもいいんだろうね、どうせもうわからないんだからさ。
ふう、四日分、おしまいっ!