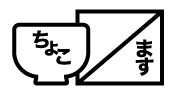2024/08/06(火)、実質移動日、朝食後、チェックアウトの12時ちょっと前までプール、
やはり、海は綺麗ではない、
プールにある看板、オオトカゲが来るらしい、ついでに、看板と言えば、ホテルとかバスとか、ドリアン禁止をちょいちょい見かける、まあ、日本でも、納豆とかくさやの臭いがその辺でしてたら嫌だわな、
ホテルの近くでランチ、なんでもない、焼きそばと炒飯が、無難に美味しい、
タクシーで移動、寺院を二つ見、かなりの雨、予定より早めに空港。ちゃんと雨対策と、それを見越して行動せんといかん。そういえば、預けたキャリーバッグが壊れてて、マレーシア航空の荷物オフィスでクレーム、どうなることやら。
空港で、香港スタイルワンタンメンと、ナシレマクアヤム、共に773円、香港スタイルってのは、揚げワンタン、ナシレマク自体はココナッツミルクで炊いたご飯でそれ自体はそういうものなんだが、ついてくるソースが辛くて子供はNG、もれなくついてくる、きゅうり、ゆでたまご、ピーナッツ、揚げ小魚、の組み合わせも意味がわからない。
スタバのカフェラテビック、686円、味は普通なんだが、ちとぬるい。
クアラルンプールへ戻り、ホテルまでタクシー、そこそこな時間で、長女は寝、一人セブンで買い物、タイガー500ミリ530円、ツナマヨおにぎり140円、名物カレーパフ107円、サンドイッチ180円、食べ物は安く、酒は高い。
コンビニからの帰り、ツインタワー